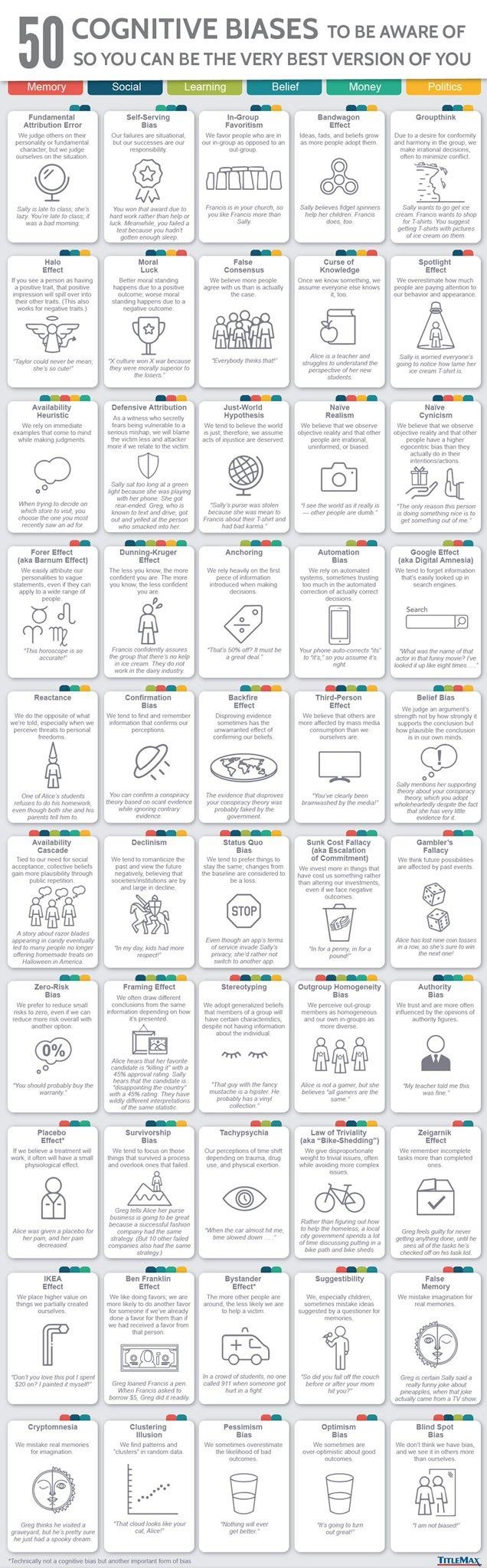2022年、30日が仕事納めでした。
1年を通して、前半は辛い時期もありながら、最後にはとてもいい1年だったと言える年に出来たと思います。
振り返っていきたいと思います。
「「「「「「「「「
年初はとても辛いスタートでした。
というのも、仕事の受注が芳しくなく、とにかく時間を持て余していました。1~2月中旬まで鬱状態だったと思います。
現場はなくて構わないから、やりたかったことを始めようとそこから復活して、4月の繁忙期を迎えて、やっと鬱状態から戻ってきました。
繁忙期は不要なことを考える必要はなくてありがたいです。
私は暇で鬱になるということがわかりました。そんなことは決してないのに、自分が世の中から必要とされていないような感覚に陥ってしまいました。
自分が暇が耐えられないことを知れたことはとても大きな財産です。
知っていれば陥りづらくなるし、そうなった時に自分で気付いて戻ってこれる気がしています。
8月まではとにかく忙しくしていて、あまり記憶にありません!
9月からブログを週一で投稿開始することにしました。
ここからインプットとアウトプットを繰り返すことにより、少しずつですが自分の考えがまとまっていくような学びの気持ちよさを感じることになりました。
SNSをツイッターメインで活用することにより、尊敬する方からいいねをいただいたり、フォローバックいただいたりととても嬉しいことが次々と起こりました。
自分の考えや感じたことをまとめる場としての活用とはいえ9月から投稿したブログはほぼみる人がいない。妻からはそれを揶揄されました。
確かにな。という気持ちと、やはり恥を打ち捨てて事を成さねばならぬ、という坂本龍馬の言葉に心を打たれて、11月23日に本格的にnoteを開始することにしました。
11月のはじめにHHKBという高級キーボードを購入し、文字を打鍵する楽しみを生活に取り入れて記事づくりがさらに楽しくなる環境づくりに取り組みました。
イヤホンはAirPodsPro(第2世代)、パソコンもついにMacBookAir(M2搭載)を購入しました。入力する環境を整えるととても楽しくなることに気付きました。(あとはマウスですね^^)
ブログやnoteを今年スタートしてから気付いたこと。
今感じてることを今書き留めることは今の自分にしかできないこと。
10年後の自分に、今の自分の感じたことは書けないはず。
考えの若さや、歳とともに変わる思考と老いていく体の状態が今の自分と違うから。
書きながら目覚める決意だったり、インプットしたものからの気付きを言語にして残すことが自分にとってとても大切になっています。
学び、発信するということについて、とても前進した1年となりました。
インプットして、アウトプットすることは当然として、
そこで満足せずに、実際に行動を起こすことが次の成長の段階だと感じています。
僕のコツコツ積み上げはまだ始まったばかり。
来年もしっかり取り組んでいくことを書き残して、今年最後のnoteとさせていただきます。
来年も自分の思考や思想を少しでも伝えられるようなnoteを書いていきたいと思います。1年間ありがとうございました!
よい年越しをお過ごしください!